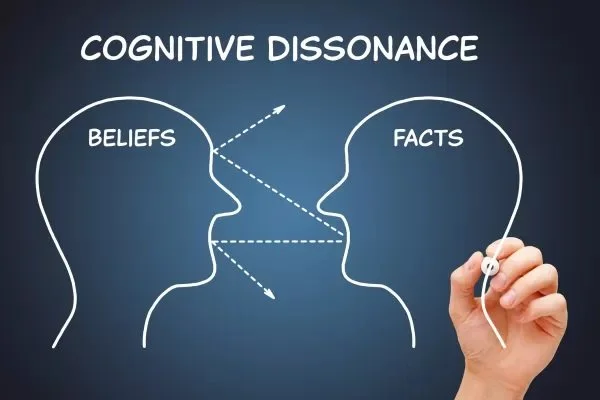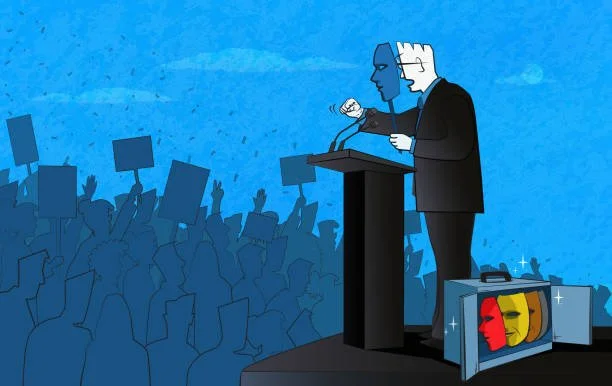嘘つきが跋扈する時代
エス・アイ・エム
代表コンサルタント(認定心理カウンセラー)
佐藤 義規
昨年12月に The Stellar Journal に書いた「泥棒に隷属する愚かさ」(※1)の中で「多くの国民が、不倫した芸能人や一般人の不適切な行いや犯罪行為に対しては過剰なほどのバッシングを行うにも関わらず、不正や嘘を重ねた政治家に対しては異常なほど寛容です。また、民主主義に限界を感じてなのか、強力なリーダーシップを願ってのことなのか、そうした政治家を支持するだけでなく、専制や独裁を願うような人たちまで出ています。」と述べました。
今回の参議院選挙では、参政党の候補や支持者らが、嘘やデマを拡散させ、その嘘を前提とした主張と共に色々な人や集団を批判しました。結果としてそれを信じた有権者の支持を得て大きく得票数を伸ばすことに成功しています。例えば、参政党の神谷代表は「宮城県が水道事業を外資に売った」と演説で述べました。これに宮城県が事実ではないと抗議しましたが、未だに騒動は続いています。(※2)
また、静岡県の伊東市長の学歴詐称問題(※3)など、他にも嘘が問題となっているニュースが連日報じられています。
伊東市長の学歴詐称問題は、学歴詐称という一つの嘘から始まり、保身のために嘘を重ねているように見えます。真偽は未だ不明ということになっていますが、卒業した事実が無い(※4)以上は、公職選挙法235条に抵触し、公職選挙法違反であり、また軽犯罪法第1条15号に違反する犯罪でもあります。また、卒業証書を偽造した、もしくは誤認させるような書類を作ったのだとすれば、私文書偽造・行使罪の疑いも出てきます。
類似の学歴詐称問題は、日本だけではなくスペインでも大きな問題になっているようです。(※5)もっともこちらは早々に辞任という形で決着したようですが。
そもそも学歴は社会的ステータスの象徴で、その人の能力や信頼性を担保する記号的役割を持っています。社会心理学者 Erving Goffman の自己呈示理論(※6)によれば、公職者は市民に対し「能力と誠実さ」という Front region を演じる存在であり、その人の能力や信頼性を担保する記号的役割に虚偽が混じれば、市民はその人の Back region を暴かれた感覚を持ち、矛盾する二つの認知を抱えることになります。これを認知的不協和と言います。アメリカの心理学者 Leon Festinger が提唱した認知的不協和理論(※7)によれば、認知的不協和は整合的な情報で解消されるべきであるが、発言が揺らぎ続ければ不協和は増幅し、信頼は加速度的に失われるとされます。理論通りなら結末は明らかと言えそうですが、兵庫県知事の例もありますので、果たしてどのような結果になるでしょうか。古代ローマ時代にカエサルが言ったように「人は自分の信じたいものを喜んで信じる」ようです。古代ギリシャの弁論家デモステネスも、同様の言葉を残していますので、歴史的にも「人は真実であっても自分に都合が悪いことは受け入れがたい」ようですから。
嘘には、「自分のため」「他人のため」「自分と他人のため」の3つの動機と「得するため」か「損をしないため」がその3つと組み合わさって構築されます。一番多いのは「怒られないために自分を守る嘘」で、多くの場合「嘘をつく人は自分のことも騙している」のです。人は自分の中に不一致があることを嫌います。嘘をつくと、事実の不一致が生じ、それを人間の脳は嫌がるのです。認知的不協和を解消するために脳は自分をだまし、不協和を解消しようとします。つまり、自己欺瞞、都合のいいように解釈し辻褄を合わせるのです。そして嘘をつき続けると人はだんだん慣れてきます。本来人間の脳は、嘘をつくと罪悪感が生まれます。感情を司る脳の扁桃体が、最初に嘘をついたときには働きますが、何度も嘘をついていると慣れてきてしまい、罪悪感を感じにくくなります。つまり、嘘をつけばつくほど、より嘘つきになっていくのです。政治家は選挙で有権者に応援してもらわないといけないので自分をよく見せたいわけです。自分が得をするため、自分が損をしないために嘘をつく場合があるということです。
2022年に Study Finds が、米国の成人2,000人を対象に行った調査によれば、平均的な人は1日に約4つの嘘をつくと報告されています。(※8)文京学院大学人間学部の村井潤一郎教授の研究によれば、日本人はこの数字よりも少なく、男性 1.57 回、女性 1.96 回だそうです。(※9)だからと言って、アメリカ人より日本人の方が誠実だとか、優れているというようなことを述べるつもりはありません。単なる社会的地形的歴史的環境の違いから生じているものでしかないと思います。
ここで述べたいのは、村井教授の研究結果の数字と、我々が日頃から耳にする政治家の嘘(記憶にない、秘書がやった、私は知らない)を耳にする頻度との乖離が大きいということです。国会で118回もの虚偽答弁を行った元首相もいるくらいです。
また、言葉でなくても、事実を歪曲したり、都合の悪いことを隠したり、将来の約束を反故にしたりことがあまりに多く、それによって日本の社会構造が捻じ曲げられたり、国民が不幸になったり、国益を損なったりしていることも問題です。「仮に嘘だとしても、それは『国益のため』『国民のため』のものだから許されるべきだ」という意見もありますが、国益のため、国民のためという美辞で嘘を付くことが果たして今の時代に通じるでしょうか。せいぜい、外交・国防などの限定分野において極秘事項を公表しないことが許される程度でしょう。「国益のため、国民のため」を免罪符のように使わせてはなりません。
以前も取り上げましたが、英ウェールズでは政治家の「嘘」を罰する法律が可決され、2026年から施行されます。(※10)イギリスの一構成国の話ですが、注目していきたい政治の変革であると思います。日本に限りませんが、現代社会の政治を歪める要因として、政治家の嘘だけでなく、様々な人や組織が発信するデマなどの嘘や事実を捻じ曲げた情報もあります。残念ながら法制度が情報技術の進化に追いついておらず、SNSは半ば無法地帯と化しており、このまま放置すれば政治だけでなく社会全体を歪めかねないでしょう。オーストラリアでは16歳未満の子どものSNS利用を禁止する法律が可決され、Facebook、Instagram、SnapChat、TikTok、Xなどを対象として12月から施行されます。(※11)しかし、これは子供を犯罪から守るための法律であって、デマ情報に対する対策ではありません。裏付けのない真偽不明の情報が匿名で投稿されることが問題であり、投稿(発言)には責任の所在を明確にする(実名など)や閲覧数やフォロワーを増やすための扇動的な発信対策などが求められるように思います。同時に、扇動的なデマや嘘に振り回されないよう、国民一人一人が日頃から社会情勢に目を向け、アンテナを高くし、情報を精査することができるような力をつけておくべきでしょう。そうでなければ、嘘つき達に滅ぼされる未来しかありません。「信じたいこと」と「信じるべきこと」は違うのです。
※1:泥棒に隷属する愚かさ(The Stellar Journal)
https://www.stellarrisk.com/blog/f3pl7ld9j5y5yn4-2rynz-ck7dt-p4lhn
※2:参政党の神谷代表、宮城県の水道事業巡り村井知事が申し入れた対談「応じかねる」…知事「逃げた」(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20250806-OYT1T50227/
※3:19.2秒か10秒か…伊東市長の卒業証書「チラ見せ」 深まる不信(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/AST8G2TQRT8GUTPB00RM.html
※4:「卒業できていない事実を東洋大と争う考えない」 静岡・伊東市の田久保真紀市長(産経新聞)
https://www.sankei.com/article/20250813-2EQ45G473VKDBCTBE4QVGPXYUU/
※5:学歴詐称疑惑で辞任相次ぐ 有力政治家ら―スペイン(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025080700656&g=int
※6:The Presentation of Self in Everyday Life (English Edition)(Erving Goffman)
※7:Theory of Cognitive Dissonance(Leon Festinger)
※8:‘You look great!’ Average person tells 4 lies per day, survey shows(StudyFinds)
https://studyfinds.org/average-person-tells-four-lies-daily/
※9:科学研究費補助金研究成果報告書(国立研究開発法人科学技術振興機構:J-STAGE)
https://kaken.nii.ac.jp/en/file/KAKENHI-PROJECT-20730405/20730405seika.pdf
※10:英ウェールズ、政治家の「嘘」を罰する法律を可決(IDEAS FOR GOOD)
https://ideasforgood.jp/2024/09/06/compassion-in-politics/
※11:オーストラリア、16歳未満のユーチューブ利用も禁止へ(CNN)
https://www.cnn.co.jp/tech/35236170.html
記事の無断転載を禁じます。
————————————————
事業運営上の様々なコンサルタント(業績改善、事業分析、戦略作成支援、人材教育など)やメンター・プログラム、心理カウンセリングなどを行っています。 お気軽にご相談ください。
エス・アイ・エム
代表コンサルタント(認定心理カウンセラー)
神奈川県川崎市川崎区京町2-3-1-503
050-5881-8006
Email: y.sato.sim@gmail.com
http://simconsul.web.fc2.com/