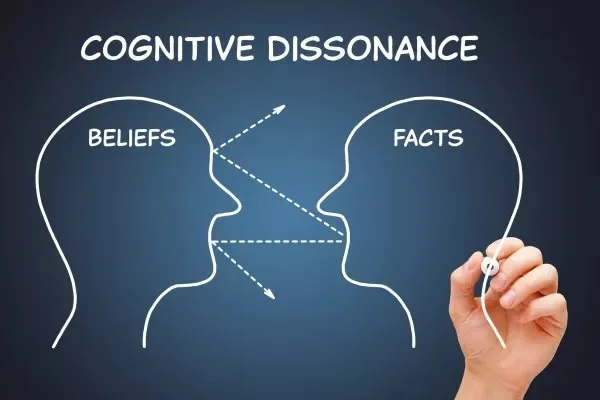The Stellar Journal
日系企業が留意すべき「企業向けマッチングアプリ」の米国でのリスク
現在日本にいる息子たちに彼女ができたそうです。で、どこで知り合ったのかと思ったら、「マッチングアプリ」という答えが返ってきました。私が若いころとは違い、現在はパートナーを恋愛マッチングアプリで探す、というのは、社内恋愛より普通のことだそうです。
ドナルド・トランプを心理分析すると
前回、『トランピズムは「終わりの始まり」』でトランプ大統領の異色性は彼自身のキャラクターとトランピズムと呼ばれるその政治手法であると述べました。彼のキャラクターと政治手法は、彼自身が「パーソナリティ障害」、それも「自己愛性パーソナリティ障害」と「反社会性パーソナリティ障害」、「演技性パーソナリティ障害」の複合型であることから来ていると個人的に分析しています。
アメリカ精神医学会が定めている『精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)』におけるB群(感情的で移り気なタイプ)に該当すると考えます。正式な診断や分析結果ではなく、あくまで個人の見解としてご理解ください。
ICEはアメリカ版ゲシュタポだ!
近頃、シカゴをはじめ全米各地で、移民・難民を標的にしたICE(米国移民関税執行局)の過激な取締りが、国民の良心を揺さぶっています。これらの行為はもはや「法の執行」とは呼べません。それは、最も弱い立場にある人々を脅し、恐怖で支配する「国家による弾圧」です。表向きは「移民取締り」でありながら、実態は残酷で非人道的な暴力へと変質しています。いまやICEは、まさしく「アメリカ版ゲシュタポ」と化しているのです。
自分の政府を恐れるようになるとは思ってもみなかった!
本号で、佐藤義規氏が「トランピズムは『終わりの始まり』」という記事を寄稿してくださいました。その中で佐藤氏は、アメリカの民主主義が権威主義の手口によって、レンガを一つひとつ壊すように崩されていく現実を描写しています。その言葉は決して誇張ではありません。今私たちは、自由の国アメリカが恐怖と威嚇の国へと変わりつつある瞬間を目の当たりにしています。
トランピズムは「終わりの始まり」
今やトランプ米大統領の言動について、見聞きしない日はありません。それだけアメリカ大統領の世界に与える影響が大きいということですが、それだけでなく彼のリーダーとしての特異性が関係していることは誰もが認めるところでしょう。彼の異色性は彼自身のキャラクターとトランピズムと呼ばれるその政治手法によるものです。
嘘つきが跋扈する時代
昨年12月に The Stellar Journal に書いた「泥棒に隷属する愚かさ」の中で「多くの国民が、不倫した芸能人や一般人の不適切な行いや犯罪行為に対しては過剰なほどのバッシングを行うにも関わらず、不正や嘘を重ねた政治家に対しては異常なほど寛容です。また、民主主義に限界を感じてなのか、強力なリーダーシップを願ってのことなのか、そうした政治家を支持するだけでなく、専制や独裁を願うような人たちまで出ています。」と述べました。
アメリカには育児休職制度はないの?
日本から来たばかりの方に聞かれました。「日本には、1年ぐらい育児休業制度がありますが、アメリカにはないのですか?」結論から言うと、日本のような手厚い育児休業制度はありません。
日本では、産前産後休暇は、労働基準法で規定されており、「女性労働者の出産前後の身体的な回復を目的とした制度」です。産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、産後は出産翌日から8週間まで取得が義務付けられています。(医師が認めて、本人の希望がある場合には、産後6週間)。
アメリカの徴兵制とジェンダー平等
現在(2025年7月)、アメリカでは徴兵制はありません。しかし、世界で戦争が終結していなく、ドイツではまた徴兵制を復活するかもしれない、というニュースを聞くと、アメリカでもまた徴兵制が復活するのではないか、と心配になってきてしまいます。